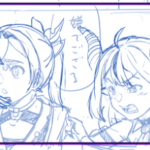傷痍軍人という国内では日常に見えなくなったテーマ

アマゾンプライムビデオやNetflixで手軽に映画を見ることができるようになって本当に便利になりました。
TSUTAYAのネット宅配レンタルを使っていた時は、自分で見るべき映画をリストに選定しておいて一つ一つ今月はこれを借りると見定めをしなければなりませんでした。
郵送、返却の手続きがあるもんだから物理的時間的な上限があったのですね。
それに比べるとネット配信は、ジャンル絞りや監督絞りでの作品の一気見がとても楽になりました。
ゴダールだとかフェリーニだとか、なんというか勉強のために一応見とかないといけない的な作品はDVDをプレーヤーに入れるのにも気合が必要でしたから。
戦争映画ばかり見ていて気づいたこと
で、まあジャンル絞りの中で戦争映画を集中的に見る中で気づいたというか気づかざるを得なかったこと。
海外と国内で圧倒的に違うのが傷痍軍人やPTSDの扱い、情報量の格差。
国内映画だとそもそもにして戦争映画の数自体が近年だと少ないわけですが、たまに予算をかけてヒットしていてもなんというかまあアレな作品になってしまいます。
そもそも最近は日常に見える形で戦争にコミットしておらず、中東でアメリカの下請け的な動きをするくらいしかしてないもんだから作品が作りようがないって事情もあります。
無理に作ろうとすると架空戦記みたないものになって結局ガンダムみたいに最後はなんか超能力的なもので解決します、みたないシナリオになったり・・・。
英雄譚を欲していて、それはそれでエンタメとして作る必要はあるもののそこから一歩先には行けないケースが多いというかなんというか。
けれど海外ではリアルな戦争がころころ転がっているものだから、英雄譚を作るにしても陰影が出てきます。
現実の日常に戦場で傷ついた元兵士が数多く普通に生活を送っているものだから、戦争映画なんてむしろ日本の方が遥かに単純で安直な作りになってしまっている。
たとえば「アメリカンスナイパー」
クリント・イーストウッド監督作品「アメリカンスナイパー」は不思議な作品です。
ちゃんと丁寧に鑑賞すれば、どう見てもクリント・イーストウッド自体は作中で描かれるイラク戦争そのものに懐疑的であったりシニカルな立場である感じが伝わってきます。
傷痍軍人やPTSDの痛ましさもしっかり描いている。
・・・のだけども、表面的な部分だけを捉えると典型的なアメリカ人の心優しい男が父親になって、国のために勇敢に戦ったという愛国映画に見えないこともない。
だいぶ安直で読解力のない消費の仕方をしないとそういう受け取り方にはならないと思うのだけれども、どうもそういう受容のされ方もしているようで奇妙な感じがあります。
ポイントポイントだけで見れば確かにかなりベタな戦場から妻に電話をかけるシーンなどもあり、安直な愛国心鼓舞映画に見えないこともないけれども・・・全体としてはそういう映画じゃないはずです。
主人公自体が心を病んでいく過程が描かれ、その主人公が戦場でPTSDになってしまった元兵士に殺されてしまうという結構なエグイ構図になっているはずなんだけど、熱心な愛国主義者には その部分は見えていないのか、見るつもりがないのかとても不思議な受容のされ方をしている。
こういう複雑な陰影は近年の日本の戦争映画には生まれるはずがないものです。
物語の中に傷痍軍人が出てくる作品って、ふと思い返しても今敏監督作品の「千年女優(2002)」くらいだけれども、それだってもう20年近く前か。
あれだって昭和を描く過程で登場する傷痍軍人なのでかなり特殊な例です。
戦中派の世代が生きていた頃にはあった陰影
昔からこうだったわけではなく、戦中派の世代が生きていた頃の日本映画はこういう陰影がある作品が普通でした。
岡本喜八の戦争を描いた作品はド派手にドンパチやっていたとしてもほぼ確実にこういう陰影が必ず入っていました。
川端康成の「山の音」は戦場で心を病んでしまった息子が出てくるし、小津安二郎の「東京物語」は戦死した息子の嫁の家を訪ねる話なわけです。
勇ましい正義の物語が必要である場合があるとしても、その物語を掲げた結果傷つき苦しみながら生きていかなければならない損な役回りになってしまった人々をしっかり描く必要があった。
なぜならば、身の回りの日常に傷ついた人たちが実際に大勢いたから。
パト2で有名な押井節の長台詞
「あんたが正義の戦争を嫌うのはよく分かるよ。かつてそれを口にした連中にろくな奴はいなかったし、 その口車に乗って酷い目にあった人間のリストで歴史の図書館は一杯だからな。」
で言うところの「酷い目にあった人間」たちが沢山まだ生きていたわけです。
パト2の「だから遅すぎたと言っているんだ!」という後藤隊長のセリフを安直なタカ派路線の文脈で受容している層がいるのと 「アメリカンスナイパー」を安直な愛国主義として受容する層がいる現象は同じ構図かもしれない。
どちらも実際にはかなり屈折した陰影がある作品なのに表面的な消費のされ方をしてしまう。
記憶の忘却と、想像力の欠如というディスコミュニケーションの積み重ねの末に単純化された攻撃的な言説がまかり通る。
その単純さを避けようとすると浦沢直樹がマスターキートンで度々フォークランド紛争でのPTSDを描いたように、海外の戦争を経由して表現しなければいけなくなる。
SFや海外の戦争を経由しないと戦争の陰影が描けない時代に生きているのは幸福なことなのか不幸なことなのかわからないけれど、経済的余裕がなくなってきたこの国でそれを続けていられるのかどうか、それがわりと直近の問題だったりするのでしょう。